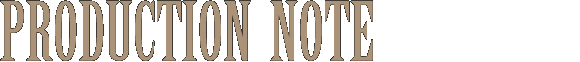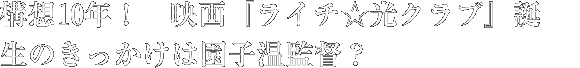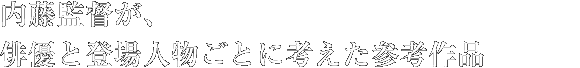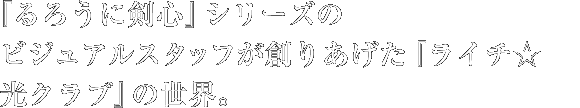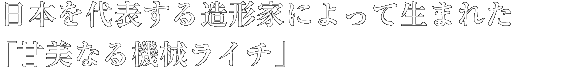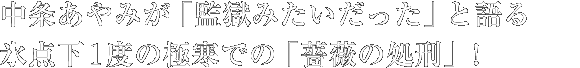撮影より遡ること10年前。本作の企画・プロデューサーである杉山麻衣が当時キャスティングを担当していた『紀子の食卓』(園子温監督)において、出演の依頼をしたのが本作の原作者・古屋兎丸氏だった。
古屋氏と園子温監督は、『自殺サークル』を漫画化して以来の縁。「マンガ・エロティクス・エフ」(太田出版刊)での連載当時より古屋氏による「ライチ☆光クラブ」のファンであった杉山が、映画化の想いを直接、古屋氏本人に伝えたのが、この映画の全てのはじまりだった。
クランクイン前、内藤瑛亮監督はキャストそれぞれとの個人面談を希望。衣装合わせの際に、一人ひとり、各キャラクターの人物像の掘り下げと演出プランについて役者と共有していった。面談の最後には「今日話した事をより掘り下げるためにも、この作品を観てきた上で現場に来てください」と伝え参考作品を俳優たちに手渡した。自分の演じる役柄をより深く理解し、そのキャラクターの芯を捉えてもらうため、監督が彼らに必要だと思った作品群は下記の通り。
- タミヤ
- ジョン・フォード監督『我が谷は緑なりき』(1950)
- ゼラ
- レニ・リーフェンシュタール監督『意志の勝利』(1942)
深作欣二監督『黒蜥蜴』(1968)
ハイディ・ユーイング他『ジーザス・キャンプ~アメリカを動かすキリスト教原理主義~』(2010) - カノン
- ブラッド・バード監督『アイアン・ジャイアント』(2000)
楳図かずお『わたしは慎吾』(漫画) - ジャイボ
- フランソワ・トリュフォー監督『アデルの恋の物語』(1976)
パティ・ジェンキンス監督『モンスター』(2004) - ニコ
- デニス・ガンゼル監督『THE WAVE ウェイヴ』(2009)
- 雷蔵
- トッド・ヘインズ監督『ベルベット・ゴールドマイン』(1998)
- デンタク
- フランクリン・J・シャフナー監督『ブラジルから来た少年』(日本未公開)
ジェームズ・ホエール監督『フランケンシュタインの花嫁』(1935) - ダフ
- ジュゼッペ・トルナトーレ監督『マレーナ』(2001)
- カネダ
- フランクリン・J・シャフナー監督『パピヨン』(1974)
- ヤコブ
- マーティン・スコセッシ監督『ウルフ・オブ・ウォールストリート』(2014)

黒い煙と油に塗れた町、螢光町。この独特の世界観を再現するためには、作り込まれた舞台を構築する必要があった。「昭和的なノスタルジー」とも「どこかの世界の未来」とも取れるような空間を作り上げたのは、映画『るろうに剣心』シリーズの橋本創。鉄と油にまみれた町と、廃工場に作られた少年たちの秘密基地を、デザイン画そのままに実際の巨大廃工場の中に完璧に作り上げ、映像としての説得力を高みへと押し上げている。
この独創的で壮大なロケセットで躍動する光クラブメンバーを始めとする衣裳デザイン・キャラクターデザインには、同じく『るろうに剣心』シリーズの澤田石和寛。各キャラクターごとにディテールの異なる学生服と学帽を用意。特に制服は、映像の「闇」に埋もれてしまわない色彩にこだわりぬいた。ダフの眼帯が、ホワイトレザーを使用しハンドメイドで仕上げられているなど、各キャラクターを象徴する小道具に至るまで徹底したことで、オリジナリティ溢れる独創的な映像世界が実現した。

既に舞台作品として人気を博している本作において、機械である「ライチ」をどのように描くべきか映画作品として大きな課題のひとつだった。
原作漫画で描かれているライチは、フランケンシュタインのような人造人間に近い形で描かれていた。映画では、14歳の少年たちが工場にある材料で作り上げたものであるという説得力を持ちながら、大人へ対抗するための兵器として圧倒されるほどの大きさを備えていることが「ライチ」の不可欠な要素であった。
そのような中、内藤監督、プロデューサーの田中勇也の共通イメージとして上がったのが、ブラッド・バード監督によるアニメーション映画『アイアン・ジャイアント』に登場する鉄の巨人だった。そのイメージと日本映画の伝統である特撮が結びつき、ライチの特殊造形物を動かすという撮影手段に向かっていく。ライチの制作は、数々の日本映画で特殊造形を手掛け、内藤監督の自主映画時代から交流があった百武朋が担当。
もともと原作者・古屋兎丸と交流のあった百武は、ライチ造形に関して映画化決定前から志願していたという。全てがつながって、稀代の造形家にライチデザインは託される。
数々のデザイン案をベースに、監督らと議論を重ねるうち、少しずつ全体的なフォルムが出来上がっていく。当初、よりスタイリッシュなデザイン案も検討されたが、教育を受けることで人間の心を手に入れていく無垢なロボット。どこか愚鈍さと恐ろしさを併せ持つような現在のデザインに集約されていく。
全体のデザインの方向性が固まっていく中で、今度は稼動領域の確保や、その物理的な制限を鑑みたアクションの検討など、様々な課題を乗り越えるために、数々のプロトタイプパーツを百武が制作し、テストが繰り返される。
テストを繰り返すうちに生まれたのがロケットパンチ。右肘に仕込まれた歯車を動力源としたライチの必殺兵器だ。大きな撃鉄を右肘の後ろに配置されることで、アシンメトリーなライチの左右半身のデザインが、より特徴的に際立つ造形となった。
無邪気なロボット作りを子供らしく夢見ていた「ひかりクラブ」メンバーのロマンが詰まった兵器。これを生み出すきっかけも彼らと同じように「こういうのはどうだろう?」「こんな構造にすると格好いい!」など無邪気で熱い議論が交わされ、百武や内藤監督らのロマンが詰まったライチが完成するに至った。
2014年12月14日、極寒の工場での撮影が佳境を迎える中、ついに「薔薇の処刑」の撮影日を迎える。この日の富士市の最低気温は氷点下1℃。鉄とコンクリートに囲まれた工場内の体感気温はさらに低く感じられる。
カノンが水の中に沈められるシーンの撮影を想定し、ジェットヒーター6台、ストーブ10台と、通常よりも多くの暖房機材を投入する。しかし、舞台になる廃工場内、玉座フロアロケセットの面積は推定30,000㎡。天井高およそ10m。全ての暖房機器を撮影3時間前よりフル稼動させても状況の改善は見られない。加えて同録撮影のために本番中はもちろん、ジェットヒーターのモーターが完全に停止するまでの時間を逆算すると、撮影準備が整ったあとは稼動すらさせられない。加えて、外気温があまりにも低く、処刑台となる棺桶に張られた水温を少しでも温めると水面から湯気が上がってしまうため、想定していた水温での撮影を断念。極めて真水に近い水温での撮影を敢行せざるを得なくなる。
既に連日撮影が10日間を過ぎ、体力的にもかなり疲労している状況の中、中条は長時間息継ぎなし、水中での演技をワンテイクでやってのけた。後に中条自身が「(廃工場に篭りっきりでの本作の撮影は)監獄みたいだった」と語った撮影の最難所を迎えたエピソードである。